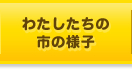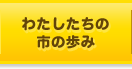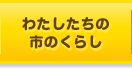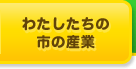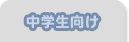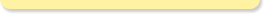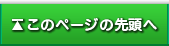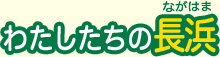歴史に残る人や文化財
小堀遠州 (1579~1647)
その後、千利休や古田織部と続いた茶道の本流を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役(しなんやく)となりました。 遠州流茶道とは?、遠州とは、どんな人物だったのでしょうか。
茶道のはじまり

小堀遠州像(長浜城歴史博物館蔵)
「茶道」で使われるお茶「抹茶」が登場したのは鎌倉時代初期でした。禅宗の一つ臨済宗を広めた僧、
一方、当時禅の修行をしていた村田
遠州流茶道とは?
千利休の心を受け継ぎながらも、香り豊かな「文化」として発展させたのが小堀遠州でした。
そして、小堀遠州を流祖とする日本を代表する大名茶道となったのが、「遠州流茶道」でした。
「綺麗さび」とよばれる精神に、「わび・さび」、美しさ、明るさ、豊かさを加え、誰からも美しいと言われる客観性の美、調和の美を作り上げました。
遠州流茶道の理念は、先人が築き上げた伝統を正しく受け継ぎ、現代に生かし、新しい創造をすることでした。
小堀遠州の生まれ

小堀遠州は豪族の長男として天正7年(1597)に生まれました。安土桃山時代から江戸時代へと遠州は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と、三者三様の社会を支配する世の中を生きました。
このことが、小堀遠州の切り開く茶道や文化に大きな影響をもつことになりました。
遠州の父、小堀新介正次は、近江国小堀村(現在の長浜市)の土豪で、母は、戦国武将浅井長政の重臣の娘でした。
父新介は徳川時代には小さな城をもつ大名までになりましたが、作介(遠州の幼名)は、この父の影響を強くうけて育ちました。
作介が10歳の頃、父は大和の国郡山城(奈良県)で秀吉の弟秀長の家老をつとめており、作介は秀長の
茶会の前日、作介は、翌日の茶会のために秀長の茶の湯の指導に来た利休と運命の出会いをしました。
利休、織部との出会い
作介が利休と出会ってから3年後、利休は秀吉の朝鮮出兵に反対して秀吉の怒りをかい切腹しました。
少年作介は、利休亡き後、お茶の世界の第一人者になった古田織部の門人になりました。
「
遠州は18歳の時、「洞水門」と名付けられた独特の手洗い鉢を作りました。それまでの手洗い鉢は、水はけがとても悪く、水が落ちるとはねたりして足もとを汚すことが多くありました。
そのため、作介は鉢の下にかめをうめて、そこに水を落とすよう工夫しました。古田織部は「これまでこんな仕掛けをこらした水門を見たことがない。
作介はひとかどの人物になるにちがいない。」と感心しました。この洞水門のしかけは、今日にも伝わっていますが、400年近くも前に遠州が発明したものです。
作事と造園
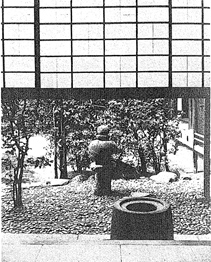
遠州作の孤蓬庵庭園
19歳の時、藤堂高虎の養女を妻にしました。このころ父は作事奉行(土木建築関係の仕事をする責任者)でしたが、作介が29歳の時に急死し、作介は小堀家をついで、そのまま作事奉行になりました。
その手腕が認められ、30歳の時、家康の居城である駿府城の建築に関わる仕事をしました。
なかでも天守閣は見事なできばえで、家康に気に入られ、「諸太夫従五位下遠江守」という朝廷の称号と位をさずけられました。作介はこのときから「遠江守」を略して、「遠州」とよばれるようになりました。
この後も、「名古屋城の天守閣」の建築の監督をするなど、作事奉行として活躍しました。
また、遠州は作庭(庭づくり)・造園でも歴史に残る功績を残しています。京都の南禅寺の庭や、岡山の頼久寺の庭園などです。頼久寺の庭は、「鶴亀の庭」と呼ばれ親しまれています。
山を背景に、白砂で波紋を作り、海を表現しました。白砂の中央には石を組みあわせて鶴島と亀島を浮かばせていました。このように遠州の芸術的な庭づくりは、「書院式枯山水」の庭として有名になりました。
一方で、天皇家のために洋風花壇のある庭づくりも進めました。これは、鎖国時代の江戸時代前期には斬新なものでした。
45歳、遠州は伏見奉行という要職につきました。「古今和歌集」を書いた藤原定家の世界にひかれ、和歌の心や文化を茶道の中に取り入れました。
このことによって、「遠州流」とよばれる茶道が誕生し、モダンな美しさ、遊び心の飾りつけなどにより「綺麗さび」という幽玄・有心の茶道をつくりあげました。
遠州は、一生のうちに400回あまりの茶会を開き、大名や公家、旗本や町人などあらゆる階層の人々を招きました。当時の「身分」を超えたわけ隔てのない茶の世界も遠州流茶道の大きな特徴でした。
遠州は相手が誰であれ、お互いを思い合う和の心を茶の最も大事な心得のひとつとしていたのです。
多彩な能力をもち、日本文化を育みながら創造的な仕事をした遠州は69歳でこの世を去りましたが、遠州の目指した精神は今も人々に受け継がれています。
教科書との関連
- 小学社会6年上54頁「今に伝わる室町の文化と人々のくらし」(日本文教出版)
- 中学社会「歴史的分野」(日本文教出版)110頁《第4編「近世の日本」⑥安土桃山時代の文化》
参考資料
- 「日本のレオナルドダビンチ 小堀遠州物語」(汐文社)
- 長浜城歴史博物館常設図録「湖北・長浜の歩み」