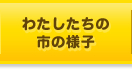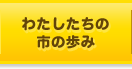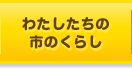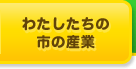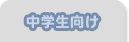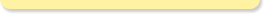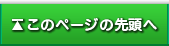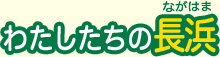ふるさとの伝統を守る
曳山 祭り
長浜曳山祭は、長濱八幡宮の祭礼として毎年4月13日から16日を中心におこなわれます。子どもが演じる曳山狂言とそれをおこなう曳山の巡行は有名で国の重要無形民俗文化財に指定されています。

曳山祭の由来は、秀吉の在城当時八幡宮の祭りで太刀渡りという武者行列を始め、その後秀吉の男子出生を祝って町民に祝金をふるまい、それをもとに各町で曳山を造って祭りで渡ったことが始まりとされています。 その後の長浜は商工都市・宿場町・湊町として発展していきます。とくに繊維業が盛んで、こうした財力をもとに曳山祭は発展していくこととなります。
17世紀後半から18世紀前半には、芸能が演じられる構造の曳山が町組ごとに造られます。
寛保3年(1742)の

曳山上部の
ここには「屋台の下にては
参考資料
- 長浜曳山子ども歌舞伎および長浜曳山囃子民俗調査報告書「長浜曳山祭の芸能」
(財団法人長浜曳山文化協会 滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科) - 長浜市曳山博物館
写真提供
- 吉田正治氏