口からはじめる健康づくり
- [公開日:2025年11月6日]
- [更新日:2025年11月6日]
- ID:9064
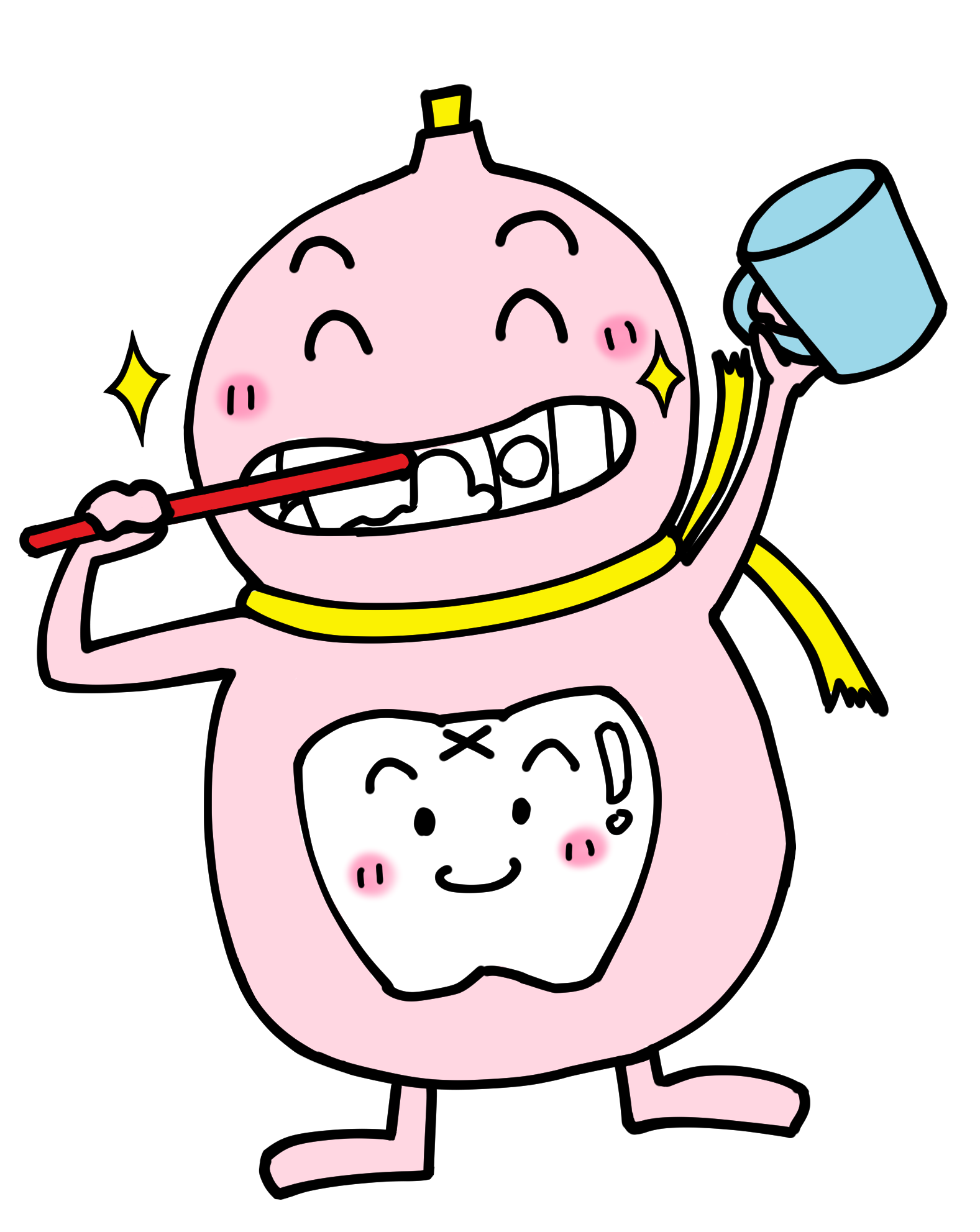
口には、「食べる」「話す」「笑うなどの表情をつくる」「呼吸をする」など、さまざまな役割があります。口の健康を維持することは全身の健康にもかかわります。自分で行う毎日の正しい歯磨きとかかりつけ歯科医による定期的な歯科健診を実践しましょう。
「ながはま はっきりことば」ができました。
いくつになっても何でも美味しく噛めるために、長浜市版のお口の体操「ながはま はっきりことば」を制作しました。大人もお子さんもみんなで楽しくお口の体操をはじめましょう。
詳しくは、こちら別ウィンドウで開く
健康な暮らしに欠かせない口の役割
口にはさまざまな役割があり、生涯にわたって生き生きと暮らしていくための基礎となります。
- 食べ物をかみ砕いて、飲み込みや消化をしやすくする
- 歯ざわりや歯ごたえを感じ食事を楽しむ
- 発音を助ける
- 豊かな表情をつくる
- 体の姿勢やバランスを保つ
- 噛むことで脳に刺激を与える
現在、自分の歯は何本ありますか?
大人の歯(永久歯)は、全部で28本、親知らずを加えると32本です。
長浜市の現状は、令和4年度健康ながはま21アンケート結果では「60歳で24本以上の歯がある人の割合」は80.2%でした。また、「80歳で20本以上の歯がある人の割合」は45.0%で、厚生労働省が発表した令和4年歯科疾患実態調査の8020達成率51.6%よりも低い状況です。
自分の歯が少なくとも20本以上あれば、ほとんどの食べ物をよく噛んで、おいしく食べることができると言われています。1本でも多く健康な歯を保つことが大切です。
歯を失う二大原因は「むし歯」と「歯周病」
むし歯と歯周病はどちらも歯を失う原因になります。
歯を失わないために、むし歯と歯周病の予防や早期発見、治療を心がけることが大切です。
中でも歯周病は口の中だけにとどまらず、歯周病菌が血液や肺に入り込んで、糖尿病や心疾患、動脈硬化、低体重児出産、誤嚥性肺炎などの全身の健康との関係も指摘されています。
歯周病の自覚症状とセルフチェック

•朝起きたときに、口の中がネバネバする。
•歯磨きすると出血する。
•硬いものが噛みにくい。
•口臭が気になる。
•歯ぐきがときどき腫れる。
•歯ぐきが下がって、歯と歯の間にすきまができてきた。
•歯がグラグラする。
このような症状があれば歯周病の可能性があります。歯科医院で検査を受けましょう。
(参考:厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイト)
むし歯、歯周病予防に毎日の正しい歯磨き
むし歯と歯周病の原因となる細菌のかたまり「歯垢(プラーク)」をなるべく口の残さないためには、毎日の正しい歯磨きが重要です。特に、就寝前の歯磨きは1本ずつ丁寧に磨くようにします。
私たちの口の中は生涯のうちに幾度となく変化をしています。年齢に限らず、妊娠や糖尿病などといった個人の体調によっても変わります。
口の中の変化に合わせて、歯ブラシを選ぶ、歯ブラシの当て方や動かし方を変える、必要に応じてデンタルフロスやフッ素入り歯磨き剤などを活用するなど、「磨けている」状態にすることが「正しい歯磨き」です。
一度は観てほしい! むし歯予防動画「ピカリンとむし歯のひみつ」
「むし歯になった時はどうしたらいいの?」、
「むし歯にしないためにはどうすればいいの?」など、
家族みんなで楽しく学べる5分間のおはなし動画です。
家族みんなで「お茶でバイバイ!むし歯菌」
※上の画像をクリックすると視聴できます。
歯磨きの習慣とともに、「のどが渇いたらお茶を飲む」「ご飯やおやつを食べた後にはお茶を飲んで食べかすを流す」など、糖分を含まない飲み物を飲む習慣を心がけましょう。
むし歯予防啓発「お茶でバイバイ!ムシバイキン」誕生まではこちら別ウィンドウで開く
定期的に歯科健診を受ける
少なくとも年に1度は歯科健診を受けましょう。
【歯科健診でしてもらえること】
- むし歯や歯周病などの病気のチェック
- 正しい歯磨きの指導
- 歯のクリーニングや歯石の除去
歯医者さんの情報はこちら→湖北歯科医師会ホームページ別ウィンドウで開く、長浜保健所歯科マップ別ウィンドウで開く
市の歯科の取組み
長浜市では、幼児の歯科健診やフッ化物塗布、19歳以上の人を対象にした歯周病検診、むし歯予防や歯周病予防などをテーマにした出前講座などを実施しています。ぜひ、お口の健康づくりに役立ててください。
【その他、歯科に関連のある市の取組み】
- 「ながはま きゃんせ体操」でいきいきと自分らしい生活を。 「ながはまきゃんせ体操」
- タバコによる健康への影響について正しく知ろう。タバコの煙による健康への影響と禁煙
お問い合わせ
長浜市健康福祉部健康推進課
電話: 0749-65-7759
ファックス: 0749-65-1711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


